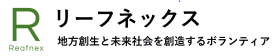多様な働き方と生産性向上の実現

目次
はじめに
日本の労働環境は大きな転換期を迎えています。リモートワークの普及、副業・兼業の解禁、フリーランスの増加など、働き方の多様化が進む一方で、日本の労働生産性は依然として主要先進国の中で低いという課題を抱えています。長時間労働が常態化し、業務プロセスの非効率性が解消されないまま、多くの企業が「労働時間=成果」と考える文化を引きずっていることが一因です。
労働生産性の国際比較2023 | 調査研究・提言活動 | 公益財団法人日本生産性本部
- 1.日本の時間当たり労働生産性は、52.3 ドル。OECD 加盟 38 カ国中 30 位。
OECD データに基づく 2022 年の日本の時間当たり労働生産性(就業 1 時間当たり付加価値)は、52.3 ドル(5,099 円/購買力平価(PPP)換算)。OECD 加盟 38 カ国中 30 位だった。順位でみるとデータが取得可能な 1970 年以降、最も低い順位になっている。2021 年と比較すると、実質ベースで 0.8%上昇した。- 2.日本の一人当たり労働生産性は、85,329 ドル。OECD 加盟 38 カ国中 31 位。
2022 年の日本の一人当たり労働生産性(就業者一人当たり付加価値)は、85,329 ドル(833 万円/購買力平価(PPP)換算)。ポルトガル(88,777 ドル/866 万円)のほか、ハンガリー(85,476 ドル/834 万円)やラトビア(83,982 ドル/819 万円)といった東欧・バルト海沿岸諸国とほぼ同水準となっている。順位でみても、1970 年以降で最も低い 31 位に落ち込んでいる。- 3.日本の製造業の労働生産性は、94,155 ドル。OECD に加盟する主要 34 カ国中 18 位。
2021 年の日本の製造業の労働生産性(就業者一人当たり付加価値)は、94,155 ドル(1,078 万円/為替レート換算)。これは米国の 6 割弱(56%)に相当し、フランス(96,949 ドル)とほぼ同水準。2000 年にはOECD 諸国でもトップだったが、2000 年代に入ると順位が低落するようになり、2015 年以降は 16~19 位で推移している。
現在の日本における少子化と人口減少を踏まえると、生産性の向上を実現するためには、単なる「働き方改革」にとどまらず、業務そのものを見直す必要があります。効率的なコミュニケーションとコラボレーションを促進する仕組みを導入することが不可欠です。
特に、日本では依然として会議、メール、電話といった従来型のコミュニケーション手段に依存しすぎており、これが迅速な意思決定を妨げ、結果として生産性の低下を引き起こしています。
そこで注目されるのが、オープンソースのビジネスコミュニケーションツール「Mattermost」です。リアルタイムチャット、タスク管理、外部ツールとの連携機能を活用することで、無駄な会議やメールを削減し、チーム全体のパフォーマンスを向上させることが可能になります。
本記事では、Mattermostを活用して「日本の労働生産性の課題を克服し、多様な働き方を実現する方法」について解説します。さらに、企業や自治体における活用可能性を探り、これからの時代に求められる「生産性の高い働き方」を考察していきます。
Mattermostとは?

多様な働き方を実現するためには、スムーズなコミュニケーションと情報共有が不可欠です。しかし、従来のメールベースのやり取りでは、情報が分散しやすく、リアルタイムな連携が難しいという課題があります。さらに、無駄な会議や重複した情報共有が発生し、結果的に生産性が低下することも少なくありません。そこで注目されているのが、オープンソースのビジネスコミュニケーションプラットフォーム「Mattermost」です。
Mattermostは、SlackやMicrosoft Teamsのようなチャットベースのツールですが、最大の特徴は自己ホスティングが可能であり、高いカスタマイズ性と、米空軍やNASAの基準を満たすセキュリティ性能を備えている点です。企業や自治体が独自のサーバー上に構築できるため、クラウドサービスに依存せず、機密情報も安全に管理できます。これにより、セキュリティを確保しつつ、チームの生産性を高めることが可能となります。
また、Mattermostはリアルタイムでのやり取りだけでなく、非同期のコミュニケーションにも適しており、働く場所や時間に制約を受けない柔軟な働き方をサポートします。例えば、異なる地域にいるメンバーが時間差で情報をやり取りしながらプロジェクトを進めることが可能です。この非同期コミュニケーションにより、無駄な待機時間や重複作業を減らし、業務効率を最大化できます。
さらに、Mattermostは多様な外部ツールとの連携が可能で、JiraやGitHubなどの開発ツール、ZoomやGoogle Driveなどのビジネスツールと組み合わせることで、業務の効率化を図ることができます。これにより、複数のツールの情報を一元化して、プロジェクトの進捗やタスク管理をスムーズに行うことができるため、時間を有効に活用し、生産性向上に繋げることができます。
次の章では、Mattermostを活用してどのように多様な働き方を実現できるのか、具体的な活用例を交えて解説します。
Mattermostが可能にする多様な働き方

働き方の多様化が進む中で、企業や自治体では「どこでも働ける環境」と「生産性の維持・向上」の両立を求められています。特に地方では、リモートワークを活用した人材確保や、地域を超えた協業の仕組みが重要になっています。
Mattermostは、こうした変化に柔軟に対応しながら、個人や組織が柔軟につながる環境を提供するツールとして、大きな可能性を秘めています。そして、働き方の柔軟性がウェルビーイングとワークライフバランスの確保につながることによって、生産性向上にも大きく貢献することでしょう。
リモートワークの推進
Mattermostを活用することで、リアルタイムかつ非同期のコミュニケーションがスムーズに行えます。従来のメールではやり取りに時間がかかり、意思決定が遅れることがよくありました。しかし、Mattermostではチャネル機能を活用して議論を整理しながら進めることができるため、場所にとらわれずにチームの生産性を維持できます。これにより、遠隔地にいるメンバーとの協力もスムーズになり、業務の効率化が図られます。
例えば、地方に住みながら都市部の企業と連携する場合、Mattermost上でプロジェクトごとに専用のチャンネルを作成し、進捗状況やファイルを簡単に共有することで、リアルタイムに業務を進めることができます。
また、すべての業務のやり取りが記録として残るため、新しくチームに参加するメンバーも過去のやり取りを迅速に把握することができ、引き継ぎ作業の負担軽減にもつながります。
地域を超えたコラボレーション

地方の中小企業や自治体が成長するためには、地域内のリソースに頼るだけでなく、都市部や他の地域とのコラボレーションを強化することが不可欠です。しかし、地理的な制約があると、情報共有や迅速な意思決定が難しくなることがあります。そこで、Mattermostのようなツールを活用することで、物理的な距離に関係なく、地域を超えたチームを形成し、リアルタイムでの情報共有や円滑なプロジェクト推進が可能になります。
例えば、地方の観光プロジェクトを進める際に、都市部のマーケティング会社やフリーランスのデザイナーと連携する場合、Mattermostを使って専用のチャンネルを作成し、関係者を招待することで、物理的な距離を感じることなく意見交換や進捗管理を行うことができます。これにより、地域間の壁を越えた効率的な情報共有が実現し、地域や業界の枠を超えた協力体制が築かれ、新たなビジネスやイノベーションが生まれる可能性が広がります。
情報共有の効率化

多様な働き方を実現するためには、単なるチャットツールとしての活用にとどまらず、Mattermostをナレッジ共有のプラットフォームとして活用することが重要です。特に、業務の進行やプロジェクトの詳細が個人に依存しがちな環境では、Mattermostを活用して情報を蓄積し、チーム全体で共有することが、属人化リスクの排除や生産性向上につながります。
例えば、地方自治体のDX推進プロジェクトでは、異なる部署や関係者が協力し合って進める必要があります。Mattermostにプロジェクトのガイドラインやマニュアルを蓄積し、適宜アップデートすることで、新たに参加するメンバーもスムーズに業務を引き継げます。また、タスク管理機能や外部ツールとの連携機能を活用することで、業務の見える化と効率化が進み、プロジェクト全体の進捗状況を把握しやすくなり、属人化を防止できます。
生産性向上への貢献
働き方の多様化が進む中で、単に「柔軟な働き方ができる」だけでは十分ではありません。企業や自治体が持続的に成長するためには、限られたリソースでいかに生産性を向上させるかが重要です。Mattermostは、単なるコミュニケーションツールにとどまらず、業務の効率化や意思決定の迅速化を実現するための強力なプラットフォームとして活用できます。
本章では、Mattermostがどのように生産性向上に貢献できるのか、具体的な方法をいくつかのポイントに分けて解説します。
業務の効率化と情報の一元管理
従来の業務では、メール・電話・会議など複数の手段を使い分けて情報共有を行うことが一般的でした。しかし、これらの方法では情報が分散し、必要なデータを探すのに時間がかかるという課題がありました。Mattermostでは、すべての会話やファイルをチャンネルごとに整理できるため、必要な情報を即座に見つけることができます。
例えば、あるプロジェクトに関する資料がメールの添付ファイルとして送られた場合、後から関係者がそれを探すのは非常に手間がかかります。しかし、Mattermostのチャンネルに資料をアップロードしておけば、強力な検索機能を活用して、瞬時にアクセスできるため、無駄な時間を削減できます。さらに、スレッド機能を利用することで、会話の流れを整理し、議論のポイントを明確にすることが可能です。これは、LINE WORKSなどのタイムライン形式とは異なり、より整理された情報管理を実現します。
リアルタイムコミュニケーションによる意思決定の迅速化

生産性を向上させるためには、意思決定のスピードを上げることも重要です。特に、リモートワークや地域を超えた協業では、タイムリーなやり取りができないことが業務の停滞を引き起こすことがあります。Mattermostを活用すれば、リアルタイムでのコミュニケーションが可能となり、関係者間での意思決定を迅速化できます。
例えば、社内で重要な施策を決定する際、従来であれば、メールでの意見交換や会議の開催を待つ必要がありました。しかし、Mattermost上で関係者が集まる専用チャンネルを作成し、投票機能やリアクション機能を活用すれば、数分で合意形成が可能になります。例えば、ある新プロジェクトの進行に関する意思決定を、関係者がリアルタイムで意見を出し合いながら迅速に決定することができ、無駄な調整時間や待機時間を削減することができます。
これにより、プロジェクトの進行がスムーズになり、業務の停滞を防ぐことができます。
タスク管理との連携による生産性向上

コミュニケーションの質を高めるだけでなく、Mattermostはタスク管理ツールと連携することで、業務の進行状況を可視化し、チーム全体の生産性を向上させることができます。
例えば、MattermostはTrello、Jira、GitHubなどのタスク管理ツールと連携する機能を備えており、タスクの進捗状況をリアルタイムで把握することができます。これにより、プロジェクトチームはMattermost上でタスク更新の通知を受け取り、誰がどの作業を担当しているのか、どのタスクが完了しているかを一目で確認できるようになります。これにより、業務の抜け漏れや重複作業を防ぎ、チームの効率とパフォーマンスを最大化できます。
さらに、Mattermostには独自のタスク管理機能「Playbooks」もあり、定型的な業務フローを登録して作業を効率化することができます。例えば、業務の承認プロセスをPlaybooksに登録しておくことで、承認作業をスムーズに進め、意思決定のスピードを加速させることが可能です。これにより、生産性の向上だけでなく、プロジェクトの進行管理を一元化でき、チーム全体の業務効率化が実現します。
外部ツールとの統合による業務の自動化
Mattermostの強みの一つは、外部ツールとのシームレスな統合が可能で、業務の自動化を加速できる点です。APIを活用することで、さまざまなシステムと連携し、ルーチンワークの効率化を実現できます。これにより、業務フローの自動化が進み、日々の手間を削減することが可能になります。
例えば、MattermostとTrello、Jira、GitHubをWebフック機能で連携させることで、プロジェクトやサポート担当者が担当する情報を一元的に管理でき、業務負担を軽減するとともに、作業に集中する時間を確保できます。
また、地方自治体のDX推進の観点からは、現有の行政システムとMattermostをAPIで連携させることが可能なため、地方自治体のDX改革に迅速に対応でき、業務の効率化が進みます。この結果、職員はルーチンワークから解放され、戦略的な業務に集中できるようになるため、職員のウェルビーイング確保にも繋がります。
まとめ:生産性向上と多様な働き方を実現するための鍵

日本の労働生産性は依然として低迷しており、企業や自治体が抱える課題は山積しています。特に、無駄な会議やメール、電話といった従来型のコミュニケーション手段に依存しすぎている現状は、生産性を大きく制限している要因の一つです。
しかし、働き方の多様化が進む今、これを克服するための鍵となるのが「効率的なコミュニケーション」と「コラボレーション」の仕組みを導入することです。
その中で、オープンソースのビジネスコミュニケーションツール「Mattermost」は、単なるチャットツールの枠を超え、米空軍やNASAの要件を満たすセキュリティ条件下において、チームの生産性を劇的に向上させるための強力なプラットフォームとして注目されています。
リアルタイムと非同期のコミュニケーションを駆使し、情報共有や意思決定を迅速に行うことができ、特にリモートワークや地域を超えたコラボレーションにおいてその効果を発揮します。
Mattermostは、従来の業務フローの非効率性を解消し、チーム全体のパフォーマンスを最大化するためのツールとして、あらゆる業種において重要な役割を果たすことができます。特に、地方における人材確保や、地域を超えた協業の仕組み作りにおいても、Mattermostは柔軟に対応可能であり、リモートワーク環境でも生産性を維持するための不可欠なツールです。
今後、企業や自治体が生産性向上を目指すのであれば、コミュニケーションツールの選定はその成功の鍵を握ります。Mattermostを活用することで、情報の一元化、業務の効率化、そしてチームの協力体制を強化し、持続可能な働き方を実現できることが期待されます。
時間や場所にとらわれず、どこでも協力し合える環境を構築することが、企業や地域の成長を支え、ウェルビーイングとワークライフバランスの調和した持続可能な未来を実現する鍵となるでしょう。
この活動は、SDGsと地方創生をテーマとし、IT技術の活用した課題解決のお手伝いをするボランティアです。この記事の内容について興味がある方は、ぜひお問い合わせください。
SDGsと地方創生に関するお問い合わせについて
どんな内容でも構いませんので、気兼ねなくご相談ください。
システムエンジニアリングの経験を持つスタッフが、ボランティアでご相談に応じさせていただきます。